(再掲時付記:長いので、最初に結論を掲げておきます。
自動車のEV化なくして脱石油も、脱化石エネルギーも、持続可能な新文明への移行もない。
以上です。では以下の行から始まります)
一連の記事では、最初に大きな戦略部分を描写してから、次にその手段として戦術・テクニカル面の詳述へと移行する、という手法を採りたい。
限界が予測されている人類社会
文明レベルの話でいえば、資源の無限性を前提とした現代文明がいずれは限界を迎えることは明白である。思い出されるのが、1972年にシンクタンク「ローマクラブ」によって発表され、世界に衝撃を与えたレポート『成長の限界』だ。これは人口増加率、資源埋蔵量と消費量、食糧供給力、経済成長などの様々な要素を勘案して、21世紀の世界をシミュレートしたものだ。その結果は恐るべきものだった。
世界人口が80億人弱に達する2020年頃には、食糧および天然資源が文明社会を支えきれなくなり、成長が限界に達する、というのである。その後には飢餓が始まり、2050年からは逆に人口が急減していく。資源量の増加や農業生産力向上のケースを想定しても、やはり急増する人口を維持できずに人類は食糧不足に陥り、結局は22世紀を待たずして人口は急減してしまう…。そんな悲観的な予測である。
驚くべきことに、当時のローマクラブの人口推計は、現在の国連のものと1億人強しか違わない。しかも、この予測には、当然ながら地球温暖化の深刻化によるGDPの損失は加味されていない。中国が将来、世界一の経済又は軍事大国となることや、欧米メジャーの石油占有率が15%以下に落ち込むことも予測の対象外だ。つまり、ローマクラブの予測当時よりも、世界はさらにコントロールが利きにくくなっている。
現在、新たに30億もの新興国の人々が先進国型のライフスタイルを目指し始めたため、化石燃料や鉱物資源の大量消費にドライブがかかっている。なにしろ、中国人がマイカーに乗り、インド人がエアコンを付け始めた。今後、10億人を擁する先進各国がエネルギー利用効率を改善し、自然エネルギーを導入し、省資源を心がけても、その節約分は優に相殺されよう。
彼らを止める権利は誰にもない。同様の行為によって先に経済を成熟させ、豊かなライフスタイルを享受してきた先進国が「環境保護」のロジックを振りかざす様は、新興国の目には「エゴ」であり、「ライバル蹴落としの陰謀」とまで映っている。
世界はすでにサバイバルレースへと突入した。当面打つ手は、あるにはある。たとえば、資源の囲い込み。とくに天然資源の乏しい国は、できる限り海外の資源権益も押さえていかねばならない。また、自国のエネルギー利用効率の改善と需給構造の改革も不可欠だ。端的にいえば、経済成長を損なうことなく、より省エネを進め、代替エネルギーの比率を高めていかねばならない。今や、多くの国がこの方向にむかって動き始めている。
人口を減らすことも、有力な選択肢だろう。ひとりの人間が文明的な生活をするためには、莫大な水・食糧・エネルギーが必要だ。よって、これらの資源が希少化する時代にあっては、人口が多ければ多いほど、全体として文明生活を維持するのが難しくなる。自然に減少に転じている日本の状況は、見方によっては天恵といえる。
フロー系エネルギーのコントロールに成功したのはごく最近
だが、これらは対症療法にすぎない。長期的には、人類が持続可能文明へと移行しなければならないことは明らかだ。先んず、エネルギー分野での達成が求められる。なぜなら、エネルギーこそが文明の基礎であり、原動力だからである。
そのためには、化石燃料などのストック系から、枯渇しないフロー系(自然エネルギー)へと、メインエネルギーの比重を徐々に移していく必要がある。
このフロー系とは、光が降り注ぐ、風が吹く、水が循環する、地が熱をもつ…といった自然現象を指している(それゆえ「自然エネルギー」という用語は正しいと思う)。原発がGWなら、これらはPW(ペタワット)クラスの量的規模である(*ただし利用可能量は別問題である)。
ちなみに「近代前の世界は、産業・運輸・家庭の全分野にわたり、自然エネルギーに依存していた」という誤解が根強く存在している。正確には「バイオマスに依存していた」と表現すべきである。これは再生可能な“ストック系エネルギー”だ。
このバイオマスでは近代文明のエネルギー需要を満たせないので、人類が石炭・石油などの地下資源に手を伸ばしていったのは当然の経緯である。
対して、水力・太陽光・風力などのフロー系のエネルギーは、もともと賦存量(物理的限界潜在量)が膨大であるにもかかわらず、技術的な制約から、その場限りの動力として、ほんの少ししか利用できずにいた。たとえば、船の帆とか、風車・水車などである。電気技術の進歩により、初めてそういった気まぐれなエネルギーを大規模かつ定量的に利用できるようになったというのが事実である。
つまり、人類が自然エネルギーをまともにコントロールできるようになったのは、比較的最近の話なのである。前回にも言ったが、もっと難しいのが原子からエネルギーを取り出すことだ。そういう意味で、自然エネルギー社会より前に原子力社会が訪れることは不自然に思われる(*ニュー原子力の「芽」は出ているので、今世紀後半になると思う)。
ある意味、すでに学問用語・法律用語となってしまった英語のrenewableと、その訳語である「再生可能」が混乱を引き起こしている原因かもしれない。なぜなら、厳密には、薪であれ化石燃料であれ、ストック系エネルギーはみな、日本語でいう「再生可能」だからである。地球レベルでいえばどちらも炭素循環における一形態でしかない。
ただし、薪は数十年で再生するのに対し、石炭や石油は数百万から数千万年かかるだけの違いで、人間の主観(時間尺度)でみれば一方が再生可能、もう一方が枯渇性に思えるだけの話である。
ただし、ここまで科学的な正確さにこだわると屁理屈になってしまうので、私は個人的にフロー系のそれを「自然エネルギー」、ストック系内のバイオマスを「再生可能エネルギー」というふうに、両者を使い分けるにようにしている(*これは私が勝手にやっていることで、一般的にはやはり「再生可能エネルギー」で統一されるのがよろしいかと)。
脱化石エネルギーを達成するための三つの対策
さて、フロー系のメイン化によりエネルギーシステムを持続可能化するということは、換言すれば「エネルギーの永久自給国」へと進化することに他ならない。たとえサウジアラビアであっても、資源を切り売りする限りいつかは枯渇する。そういう意味において、永久自給国になることは「永続する富」を手に入れるに等しく、いかなるエネルギー資源国よりも富める国であり、優越する立場である。当然、そこへ至るには「脱化石エネルギー」を成し遂げることが不可欠だ。そのためには平行する三つの作業が必要である。
第一:最終エネルギー消費における電力の割合を高めていく
現在、家庭・業務・産業・運輸の全部門のエネルギー消費量は約4兆kWhであり、電力化率はその四分の一程度に留まっている。残りの約3兆kWhは、ガソリンや都市ガスなど、化石燃料製品の消費である。この部分を電気エネルギーに転換していくことが必要だ。世の中には、「坊主憎ければ袈裟まで憎い」がごとく、反原発のあまりEVとオール電化まで敵視している人たちがいるが、脱化石エネルギーのためには国家の準オール電化は避けて通れない道だ。
第二:持続可能な電源の割合を増やしていく
要は太陽光・風力・地熱発電などである。これに関しては「真の電力改革と自然エネルギー普及策」で、私は三次元に分けて導入する独自の方法を提唱した。個産個消のレベルでは太陽光と風力、町村などの地産地消のレベルではその地元で採れるもっとも豊富な自然エネルギー、都市のレベルでは大型の自然エネルギーである水力・地熱・風力・海流、という具合に。
各自然エネルギーの長短を考慮すると、次元ごとにそれぞれ適切なそれがあることが分かる。将来的には、クリーンで持続可能な「ニュー原子力」も有力な候補である。自然エネルギーと原子力は本質的には対立しない。逆にいえば、今の「オールド原子力」からは戦略的に脱していく必要があり、福一事故は撤退のサインだと思う。
第三:エネルギー消費量そのものを減らしていく
これには二つの方法がある。人口減と省エネである。少子高齢化により、2050年には、日本の人口は1億人程度になると言われている。ただし、減少自体は結構なのだが、人口構成が歪すぎるのも問題だ。
平行して省エネも進めていかねばならない。ちなみに、省エネとは「同じ仕事を以前よりも少ないエネルギーで果たせるようになる」という意味で、節電とは分けて考える必要がある。照明をLEDに変えるといった省エネもよいが、もっと効果的な方法は需給構造そのものを変革する手法で、それは「日本国のエネルギーの流れと超省エネ法の紹介」で触れた。
以上の三つの方法を平行して進める必要がある。私の考えでは、2050年に日本のエネルギー消費量を3兆kWh以下にもっていくことは十分に可能だ。そして、電力化率を三分の二以上にもっていく。つまり、電力需要が今のほぼ倍――2兆kWh以上となる。その大半を自然エネルギー発電で支える。残りの1兆kWh枠でも、できる限りバイオ燃料・バイオガス・持続可能水素の比率を増やし、化石燃料の消費は抑える。このような状態に達して、はじめて「日本のエネルギーシステムは持続可能化した」と言えるだろう。
ただし、今の電力システムを踏襲する形では絶対に無理である。とりわけ、FITでミニ発電所をそこら中に立てまくり、それに合わせて送電線を膨張させていく恣意的な方法では、最終的に2兆kWhもの発電量を確保できるわけがない。必ず途中で頓挫する。
今言ったように、「個産個消」「地産地消」「都市ごとの商用電源」の三次元に分けて自然エネルギーの導入を進めることが、最小限の費用で最大の効果を挙げる道筋である。
むろん、技術的に可能ということと、経済的に可能ということはまったく別問題である。このようなシフトは、あくまで経済的に無理のない範囲で行わなければならない。
自動車のEV化なくして脱石油もなし
さて、以上のような話がどうEVに繋がっていくのか。それは、こういうことである。
上の第二の策では、当面は自然エネルギー発電の普及が対策となる。一方で、第一の、「エネルギー消費における電力の割合を高めていく」策では、「石油製品の消費をいかに電力へと置き換えていくか」が鍵となる。なぜなら、今日、約4兆kWhにおよぶエネルギー消費量のうち、石油製品が2兆kWhも占めているからである(だから現代は「石油文明」なのだ)。しかも、その半分弱が自動車燃料用途だ。98%を石油エネルギーに依存している運輸部門(*自動車9割、航空機・船舶1割)の脱石油化こそが「要」なのだ。
つまり、第一の策におけるメインが「脱石油」であり、その脱石油のメイン対策が「自動車の電化」なのである。これなくして国の電力化率を上げることはできず、当然ながら持続可能なエネルギー社会も実現しない。また、「日本国のエネルギーの流れと超省エネ法の紹介」でも触れているが、内燃車をEV化すること自体、省エネにも繋がる。
おそらく、ここで異論が出るはずである。というのも、石油の代替として「バイオマス」を筆頭に考える人が存外に多いからだ。たとえば、自動車ならばガソリンからバイオ燃料に、暖房ならば灯油から木質チップに替える、という具合である。
私はバイオマスの利用には大賛成であるが、日本の国土のバイオマス生産能力と資源量についてはある程度、知っているつもりである。
バイオ燃料車については後ほど説明するが、基本的には「技術的には自動車燃料の代替が可能であっても量的には不可能」という事情がある。つまり、バイオマスは、量的な意味で常に脱石油の補完的な役割しか果たすことができない。
考え方としては、同じ地表1平米に降り注ぐ約1kWの太陽エネルギーを使って、「太陽光発電→EV」と、「バイオマス生育→バイオ燃料車」のどちらが優れた選択か、ということである。
同じ太陽エネルギーの間接利用でも、前者の方法ならば将来的に自動車エネルギーの自給自足が可能だが、後者ならば無理だ。これはバイオマスに依存するオーランチオキトリウムでも同じことである。貴重なバイオ燃料は、ジェット機など自動車以外の運輸用途に回すべきだ。
ところで、石油消費分の2兆kWhは、すべて電力に転換できるわけではない。化学原料(ナフサ)需要が高いため、シフト先は「電力・天然ガス・バイオ燃料」の三つになる。しかも、「次の文明はメタン文明である」で述べたように、現在の技術的・経済的制約からすると、各エネルギーにまんべんなく比重がかかるわけではなく、当初はどうしても天然ガスに偏ってしまう。具体的には、EVの電力を支える発電燃料として、また代替化学原料として、いったんは天然ガスの需要が拡大する。
つまり、今ある手段を使って自覚的に脱石油していくと、必然的に一次エネルギー比で天然ガスがメイン化するので、どうしても「メタン文明」へと移行する形になる。すると、「それならば脱化石エネルギーに繋がらず、脱石油する意味がないではないか」と思われる人もいよう。
だが、これはまったく正しい選択であり、状況である。なぜなら、メタン文明は単なる通過点にすぎないし、実際に国全体としても大幅な省エネに繋がるからだ。これによって日本はいったん「ガスが主・自然エネルギーが従」のエネルギー体制に落ち着く。これでよいのである。ガスはフロー系のエネルギーとうまくコンビ化できるので、自然エネルギーの安定的な拡大を下支えし、最終的にはバックアップに回るだろう。つまり、「ガスが従・自然エネルギーが主」の、持続可能な体制への移行だ。
いつ頃に「ガスが主・自然エネルギーが従」のエネルギー体制に持っていけるかは、自動車のEV化の進展次第である。つまり、仮に2030年に日本の自動車の大半がEV又はPHVに置き換わるならば、その体制もほぼ同年頃に実現する。ここまで来れば、次の20年間で、資源ガスの需要を減らし、自然エネルギーのメイン化も可能だと思う。
自動車のEV化なくして脱石油も、脱化石エネルギーも、持続可能な新文明への移行もないのである。
2012年09月08日「アゴラ」掲載







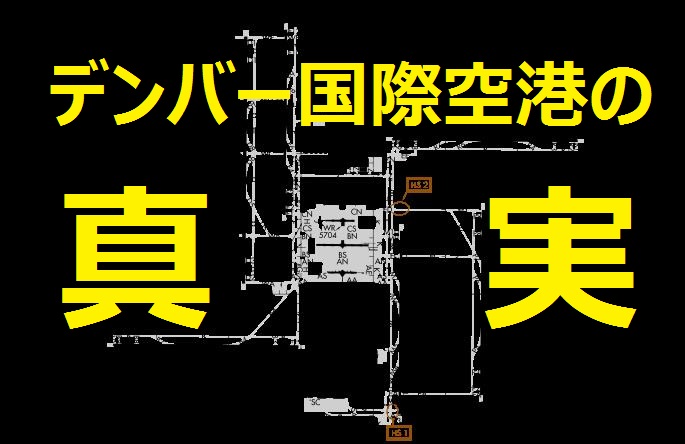




スポンサーリンク