そもそも「可採化」とは何か? 「現在の技術的経済的条件下で、ある資源の採掘が可能になった」という意味である。一言でいうなら「今ある手段でペイするようになった」ということだ。たとえば、北海道の地下1万mのところに巨大油田が見つかったとしよう。だが、1万mを掘削する技術がなければ、その資源は当然、不可採である。また、仮にその技術があったとしても、1ℓ掘り出すために千円のコストがかかっていたのでは、やはり掘る意味がないので、不可採扱いとなる。あくまで、市場販売価格以下の、数十円のコストで掘り出せるようになって、はじめて「可採化した」といえるのだ。
光が「可採化」するとは?
「光」にも同じことがいえる。光を電気へと変換する技術は、たしかに発明された。だが、1kWhの電気を生むのに数百円のコストがかかっていたのでは、わざわざ変換する意味がない。だから、当初は人工衛星用などの特殊な用途にだけ利用された。しかし、時代を経るごとにそのコストは下がっていく。現在、ようやく1kWh=数十円のところまで漕ぎ着けた。だが、それでも一般に販売されている価格よりは高い。なにしろ、電力会社は「使いたい時に使える電気」を、家庭には1kWhあたり20数円、企業にはそれより5円以上安い価格で販売しているのだ。よって、太陽光発電は、蓄電池込み価格で「1kWh=20円以下」のコストを達成しないと、市場で競争することができない。それを利用する個人・企業・社会にとって、わざわざ光を電気へと変換するメリットがないのだ。
だが、逆にいえば、これさえクリアすれば、光を電気へと変換する意味が生じる。ユーザーにとってそれを積極的に実施すべき経済的理由・動機が誕生するからだ。これをもって私は「光が可採化した」と考えている。実際、新聞や雑誌が何と言おうが、肝心の消費者は、「蓄電池込み価格で1kWh=20円」くらいのレベルでないと“グリッドパリティ”とは認めないだろう。そして、これを本当に可能にする製品として私が期待をかけているのが、今の市販品ではなく、「次世代型の高効率太陽電池」なのだ。
光を可採化させる画期的な製品
では、それはいったいどのような製品なのだろうか。
私から一つの基準を以下に示したい。
・発電効率50%以上
・耐用年数30年以上
・価格(1㎡)5万円以下
以上は一見すると平凡に思える。だが、これらの条件をクリアする太陽光パネルが、年に1千時間稼動すれば、発電コストは「1kWh=約3・3円」となるのだ。もちろん、これはあくまでパネルだけの単価である。独立した自家発電システムには、パワーコンディショナー、蓄電池、施工費、維持管理費なども含まれる。
当然、それら付随部品の性能とコストも、太陽電池同様、年を経るごとに改善されていくだろう。その前提に立つことで、仮に3・5kWの家庭用システムが70万円の価格で実現したとしよう(*パネル価格が35万円、その他の価格が35万円といったところ)。つまり、1kWあたり20万円の価格である。このシステムならば、「総コスト÷総発電量」計算で、7円弱の電力単価を実現できる。基本料金がないので、これは今の家庭用電力料金の三分の一以下である。
仮に太陽電池の性能とコストがこのレベルに達したら、太陽光発電は「市場の力」だけで急速に普及していくだろう。国や自治体からの補助金がなくても構わない。系統から離脱し、稼動後の売電収益がなくても結構。それでもなお電気料金が三分の一になるなら、需要家のとる行動ははっきりしている。逆にいえば、今のように、国や自治体から助成を付けたり、余剰電力を売電可能としている間は、いくら設置する家庭が増えても、それは消費者の本物の行動ではないということだ。テレビ、パソコン、デジカメのように、「本物」のレベルに達した製品は、政治的な方法で無理やり普及させる必要などないのだ。
実は、耐用年数と価格に関しては、現在、ほぼこのレベルに達しているものがある。ただし、発電効率は15%程度でしかない。正直なところ、そのような製品がいくら耐用年数30年・1㎡価格5万円を実現したところで、真に技術的・経済的条件を達成したことにはならない。やはり、今主流の太陽電池だと、経済的条件の変化によって一時的・部分的な「可採化」は実現するかもしれないが、本格的・永続的なそれには至らない。
どうしても「次世代型」へと進化する必要があるのだ。やはり、当初は高級機でもいいから、いったん高効率の太陽電池を市場デビューさせるべきである。その上で、その価格を徐々に引き下げていくという努力が必要だ。考えてみれば、どんなハイテク製品であれ、そのようなルートを辿ることで爆発的普及に至ったのだ。それを応援するためであれば、私はメガソーラーの建設にも賛同する。だが、今メガソーラーを建てていくと、われわれ消費者の金で中韓企業が国内シェアを制することに手を貸すようなものだ。
このように、太陽電池は「もうひと山越す」ことが欠かせない。本当にあと「ひと山」のところまで来ている。それを越せば、光が本格的に可採化する。以前の記事で、多接合、ナノワイヤー、グリーンフェライト、量子ドットといった次世代太陽電池の候補について触れたが、実のところ、どれが有望で現実的かなど、素人の私ごときに分かるはずもない。だから、開発の最前線に詳しい人から、「これがモノになりそうだから、開発にもっと資金を投じるべきだ」といった提言をしていただけると、とても助かるのである。そのような志のある寄稿に対しては、アゴラ編集部の石田さんも必ずや協力してくれだろう。
もっとも、私は楽観している。なぜなら、日本の技術者はそれまでも、もっと難しい挑戦をやり遂げてきたからである。この原稿を書いているノートパソコン一つをとってみても、日本人によるイノベーションの塊といってよい(*世界の人がそのことに無知なのはとても残念だ)。私は、日本の技術者が本気を出せば、発電効率5~6割のものが、それこそナノテクを駆使した印刷技術で製造できる未来もありうると信じている。すると、そのような太陽電池の価格は1㎡あたり数千円となろう。発電コストは1kWh=0・3円程度だ。蓄電池などを含めても、平均的世帯の月々の電気料金は千円以下になるだろう。
光が可採化すれば社会や文明がどう変革していくのか?
では、上に例示したような製品が実際にマーケットに登場すると、いったいどんな影響が生じるというのだろうか? 光が本当に可採化したら、何が起こるというのだろうか? 私の知る限り、そのインパクトについて真剣に考察した人は未だにいないようだ。それを想像してひとりで興奮していた私は、かなり不気味な存在だったかもしれない。私の考えでは次のようなことを意味し、また次のような社会現象を生じさせるだろう。
1・人間が無限のエネルギーを手に入れた。
光の資源量は無尽蔵、よって可採年数も無限だ。そこらの油田やガス田が可採化したのとは根本から意味が異なる。それは使っても使っても尽きることがない(太陽にも寿命はあるとか、そういう突っ込みは勘弁してほしい)。無限のエネルギー資源を掘り当てたのと同じだ。よって、エネルギーの「枯渇問題」は終わった、ということを意味する。
2・光は誰にも独占することができない。
日照量に差異はあるが、基本的に地上のどこでも採取可能であるため、特定の国家や企業が独占することは不可能だ。これは何を意味するのだろうか。今まではエネルギー資源が有限だったため、その所有者が主導権を握っていた。だが、誰でもどこでも手にはいる資源となると、所有者がいないに等しいので、技術や製品それ自体が重要になるということだ。つまり、地球から資源を盗んで売り捌いていた国家や企業が威張り腐る時代は終わり、新たにテクノロジーや知的所有権を有するものが主導権を握る時代が幕を開ける。「テクノロジーを制するものがエネルギー市場を制する」というわけである。
3・蓄電池の存在が不可欠になる。
太陽エネルギーは万能ではない。太陽光発電には、夜間や雨天時は発電できないという明確な欠点がある。それゆえ、その欠点を補完する蓄電池の存在がいっそう重要なものとなる。太陽光発電は蓄電池とセットではじめてノーマルな製品として扱われる。今日、家庭用や車載用としてリチウムイオン電池がメジャーだが、将来的には溶融塩電解液電池や金属空気電池などが大きくシェアを伸ばすだろう。今後、太陽光発電が「安い独立電源」として機能するようになると、ケータイやパソコンだけでなく、冷蔵庫やテレビ、照明器具までもがバッテリーを装備するようになるかもしれない。家の中、町中、至るところ蓄電池だらけとなる。よって、太陽電池の次に重要で、市場の大きい製品になるだろう。
4・エネルギーの個産個消が本格化する。
第一に、太陽電池はどこでも発電が可能である。第二に、送電線はそもそも必要悪にすぎない。よって、自家発電システムと系統電力の利便性が並べば、あとはどちらが安いかという価格の問題でしかない。そして圧倒的に前者に軍配が上がれば、消費者は容赦なく電源自立していく。お得なほうを選ぶ…当たり前の行動である。おそらく、家庭だけではなく、企業のグリッドオフも相次ぐだろう。プライベート電源と蓄電池は、どちらも少しずつ大型化することができるので、事業所のエネルギー使用量に応じた設備を整えることが可能だ。大口需要家はガス発電を併用するだろう。安定供給が可能だと分かれば、需要家にとってあとは経費の安いほうを選択するだけである。
この「個産個消」の進展がもたらす変革についてはまた機会を改めるが、少しだけ触れると、電力会社は時を経るごとに経営が悪化し、需要家密度の低い地域から順に撤退を強いられるだろう。送・変・配電コストを絶対的に背負う電力会社は、個産個消テクノロジーの前に必ず敗北する運命にある。最終的には、電力会社は日陰の多い都会の真ん中を固めることで生き残るほかなくなる。エジソン以来の、1世紀半ぶりのパラダイムシフトである。私は以上を見越した上で、常にエネルギー戦略を練っている。
5・国の電力化率が上昇していく。
突然だが、問題である。「日本の電力需要はなぜ1兆kWhなのか?」 答え。「4兆kWhに及ぶエネルギー消費の電力化率が25%前後だから」が正解。仮に太陽光発電による電力が「格安エネルギー」と化すと、家庭も企業もできるだけ電気に乗り換えようとするだろう。消費者の自主的な行動だが、これはエネルギー自給率や持続可能性向上の観点からいっても正しい選択である。自動車は当然のようにEV化していく。家庭・業務部門はオール電化によってさらにエネルギー経費を抑えようとするだろう。この三つの部門は最終的に電力化率が8割を超えるはずだ。対して、産業部門は動力系がいち早く電動化するものの、他に比べれば液体・ガス体燃料への依存が長く続く。国全体としては、電力化率が上昇していくことによって、念願の脱化石エネルギーが自然に進んでいくだろう。
6・化石燃料が次第に無価値になっていく。
われわれは石油や天然ガスそれ自体に本質的価値があるというふうに思い込んでいる。こういった固定観念は世代を超えて刷り込まれたもので、そう簡単には脱却できない。しかしながら、エネルギー資源の持つ価値は相対的なものにすぎない。仮に江戸時代に原油を桶に汲んで市場で店を開いても、誰も買わない。肥やし(ウンコ)ほどの価値もないだろう。この時代に価値があったのはタール(アスファルト)だ。灯油ランプ、次に内燃機関という利用技術の登場によって、はじめてエネルギー資源としての石油に価値が生じた。相対的価値ゆえ、利用技術が次の段階へ進むと、再び価値を失う。光の可採化により、石炭・石油・ガスなどを発電燃料として燃やす意味が無くなる。EVとバイオ燃料の普及により、石油に残るのは素材価値だけだ。植物化学や水・空気の分解合成技術の発達により、やがてそれすら失う。最後まで価値を残すのは、未だ代替手段のないアスファルトだけとなる。つまり、石油の価値は、江戸時代と同様、ウンコ以下のレベルに戻る。
以上のように、「光の時代」「光の文明」に突入すると、それまでの常識がまったく通用しなくなる。実は、細かい点を挙げれば、まだまだたくさんある。たとえば、かえって原子力の位置づけが明確になったりして、とても興味深い。おいおい述べていきたい。
いずれにしても、光が可採化すると、市場の力だけでエネルギーの個産個消が急速に進み、文明の構造自体が変化し始めるだろう。よって、ある意味、太陽電池と蓄電池の開発に巨費を投じることが最高の自然エネルギー普及策になるかもしれないのである。
2012年04月18日「アゴラ」掲載




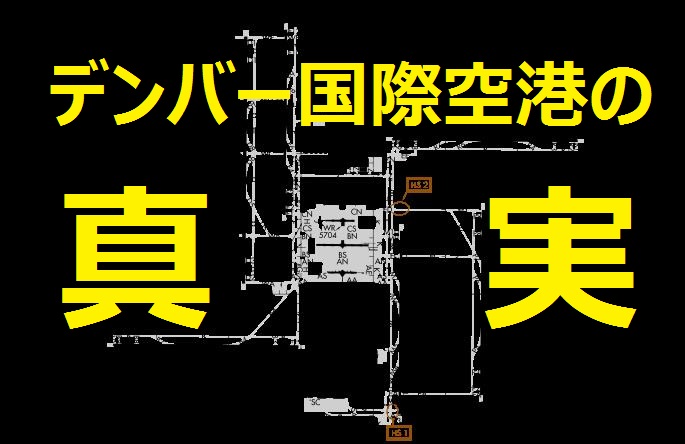







スポンサーリンク