1954年、光を電気に変える驚異的な技術がアメリカのベル研究所で発明された。太陽電池の誕生である。これによって「光」が「エネルギー資源」の一つに加わった。太陽という宇宙規模の原子力を利用した二次発電が可能になったのだ。この単純な事実は、人類の社会や文明を根底から変革する可能性を秘めている。
ポテンシャルと社会的条件の二点では「超優良」
太陽光発電のメリットとして第一に挙げられるのが、光のエネルギー資源としてのポテンシャルである。化石燃料と違って無尽蔵であり、かつ他の自然エネルギーと比べても冠絶している。ただし、供給力は限定されているので、それを正確に把握する必要がある。地球レベルの話ではなく、あくまで国内の状況を見てみたい。
09年度の統計年鑑によると、年間日照時間の最短が稚内の1394時間で、最長が宮崎の2172時間だ。ちなみに、東京は1783時間である。ただし、年によって1~200時間も変動する。太陽追尾式のパネルならば、おおむね日の出から日の入りまでの日照を捉えることができるが、固定式の場合、地域差を平均すると、1日で3時間、年間トータルで1千時間程度とされている。この値は一般のソーラービジネスで広く採用されているスタンダードな数字であり、設備利用率に直すと11・4%である(*約12%でよい)。
この、固定式のパネルが現実に利用できる直射量で、ポテンシャルを計算してみよう。地表1平米に降り注ぐ太陽エネルギーは約1kW、年間ではちょうど1千kWhだ。ということは、10キロ四方の土地十枚分に一年間に降り注ぐ太陽エネルギーだけで、日本の年間電力需要量の約1兆kWhに相当することになる。日本の面積は約37万7700平方キロだ。よって、国土に降り注ぐ太陽エネルギーは年間で約377兆7千億kWhとなる。つまり、日本列島が1日に受ける太陽エネルギーだけで、日本の全発電所の年間発電量をやや超えるというわけだ。仮に国土の数十倍に相当するEEZ内も含めれば、そのエネルギー量は想像を絶する値となる。この膨大なポテンシャルのうち、どれくらいを資源転用できるかは、太陽電池の発電効率、設置面積、経済性などにかかっている。
第二のメリットは、この巨大なエネルギーを「任意の場所」で利用できる点だ。これは発電所が基本的に「迷惑施設」であることを考えると、大変恵まれた利用条件である。
同じ自然エネルギーでも、水力・風力・地熱などと異なり、太陽エネルギーは地域的な偏りが少ない。各都道府県によって多少の日照差はあるものの、全国どの地域でも太陽が照るからだ。しかも、太陽電池には駆動部品やボイラーがなく、ダイナモも騒音もない。環境を破壊しないと考えられているため、基本的に環境アセスメントも必要ない。今年の3月に提示された閣議決定予定の規制緩和策では、工場立地法の適用外や、敷地の25%緑化義務の廃止も盛り込まれた。よって、今や国土の全域が設置対象と化しつつある。
しかも、立体ではなく面で発電するため、平地・農地だけでなく、人家の屋根やビルの屋上、建物の壁面といった、経済的に無価値な場所やデッドスペースでも利用可能だ。また、設置面積によって、家庭用の小規模発電から、都市向けの大規模発電まで自在に伸縮可能である。プライベート用であれば電力の個産個消、消費地域との近接併設であれば地産地消になり、その分、送電ロスも減らすことができる。つまり、需要家はこの尽きることのない太陽エネルギーを、好きな場所で電気エネルギーに変換し、利用することができるのだ。その特性から、まさに「どこでも発電」を実現するのが太陽光発電なのである。
一般的に、自然エネルギーは「クリーン・持続可能・国産」の三拍子のメリットを持つ。太陽光発電はそれに加え、上記のように、「エネルギー資源としてのポテンシャルが最大」と、「そのエネルギーを全国どこでも採取・利用可能である」という二つのメリットまで備えている。ただし、公平を期すために付け足すと、日本の全電力需要を賄えるポテンシャルがあるのは、地熱と風力も同様である。ただし、この二つは資源量の偏りが著しく、地理的条件に大きく制約される。また、それ以上に迷惑施設であるため、社会的条件の厳しさも災いする。よって、必然的に導入可能量が乏しくなるという欠点がある。対して、太陽光発電は、価格の問題さえ折り合いがつけば、いくらでも導入が可能だ。
このように、太陽光発電は、「ポテンシャル」「社会的条件」の二つの点では「超優良」だ。では、いった何がネックなのだろうか。それが技術的・経済的条件である。エネルギーは、われわれの家庭生活や企業活動における絶対的な基礎コストなので、どうしても「妥当な価格帯」というものが存在する。いくらクリーンで持続可能であっても、それが高価すぎれば、生活水準の切り下げを強いたり、場合によっては経済活動を破綻させたりもする。私がR水素や燃料電池車に反対しているもの、その点で問題が多いからである。
今の太陽光発電の経済性――発電効率・設備利用率・年間発電量・パネル代・原料費・維持運営費などから総合的に産出される――もまた、経済活動上、どうしても妥当な、容認できる水準とは言い難いものがある。これは何を意味するかいうと、太陽電池によって「光の資源化」は実現したが、まだ本格的に「可採化」には至っていないということである。
「グリッドパリティ」にはもうひと山
では「技術的・経済的条件を達成した」とは、具体的にどのような状態を指すのだろうか? 今、新聞や経済誌では、「太陽光発電がようやくグリッドパリティに達した」という趣旨の内容が盛んに取り上げられている。このグリッドgridというのは「焼き網」「格子」のことで、この場合は送電網のことを指す。改めて辞書を引いてみて、griddleグリル(する)が類語であることを知った。パリティparityは同等とか等価という意味。つまり、「家庭用の太陽光発電システムの経済性が系統(から給電される家庭用)電力と同水準に達した」という意味だ。技術的・経済的条件の達成とは、このような状態を指すと思えばよい。
もっとも、事実であれば、の話だ。この種の記事に共通するのは、次のような内容だ。
「電力会社から買う家庭用電気は1kWh=20数円だ。対して、太陽光発電システムの電気も20数円か、それ以下になった。これは明らかに爆発的普及の分岐点である」
このような内容を有料で読まされた読者の皆さんは、まことに気の毒というほかない。まず、太陽光発電システムを購入する際には、国と自治体から補助金が出る。この時点でその電気の経済性には、ゲタがはかされている。また、値段が同じであっても、電力会社から供給されるそれは「使いたい時に使いたいだけ使える電気」である。夜間や雨の日に系統のバックアップが欠かせない太陽光発電は、そのような供給の質・能力を持ち合わせていないし、またそれによって最低限、基本料金が課金される。「売電できる」という反論もあろうが、それは太陽光発電の普及のために時限採用されている恣意的・政治的な制度にすぎず、いずれ必ず廃止になるだろう。
そうすると、「家庭用と同程度の価格になった」からといって、軽々しくグリッドパリティなどという表現を使えないことは一目瞭然だ。似たものに、「クロスオーバーした」という表現もある。しかし、仮にアリゾナ砂漠上でクロスオーバーしたところで、われわれ日本人に何の関係があるのか。ゴビ砂漠は土地代がタダで、日照量が世界トップ水準という人もいるが、今現在でさえ、日本のすべての火力・原発設備を足した合計よりも送電線の敷設のほうがコストが上回っている事実を単に知らないのだろう。
では、真のグリッドパリティとは何か。太陽光発電システムを系統連系から外し、独立電源とする。当然、蓄電池が必要になるし、売電などというムシのいい収益もない。導入に際しては、国と自治体の補助金もない。その上で「1kWh=20円以下」を達成すること。つまり、同じ土俵の上でのガチンコ勝負で、プライベート電源が商用電源に勝つこと。これでようやく、本当の意味でのグリッドパリティが訪れたといえる。大半の消費者は、一部の物好きを除き、「面倒くさがり屋」でもあるので、このような独立電源の単価が、系統電力の単価をある程度、下回らない限り、システムの購買に動かない。逆にいえば、それを達成した時、消費者のマインドを動かすことができ、真の普及の分岐点と化す。
そう考えると、市場の力だけで普及してこそ、太陽光発電の真の普及といえる。そのためには、やはりもう一段の技術革新が必要であるというのが私の考えだ。たしかに、発電燃料費が今の数倍になるとか、倒産した大手メーカーから大量の在庫品が放出されるとか、特殊な状況が生じれば、一時的に普及の経済的条件が整う可能性はある。だが、そのような状態が安定し、持続するとは思えない。やはり、商用電源が逆立ちしても勝てないような経済格差を、プライベート電源がまったくの補助金なしで獲得する必要がある。
そのためには、前回に述べたように、今とは別物の「高効率太陽電池」を開発し、いち早く市場投入して次第に廉価化させるというプロセスを、どうしても踏む必要がある。しかも、他国に先駆けてやらなくてはならない。それなら少々コストが高くても、量産効果による廉価化の支援というわけで、メガソーラーを建設する意味も出てくる。
私は、いま実際に成果を出している国内の企業や大学の研究チームに対して、年間1千億円を十年間、総額1兆円補助することを提案したい。財源としては、エネルギー対策特別会計が有望だ。同会計は、借金の返済を除いた実質予算がちょうど1兆円ほど。その十分の一を、次世代太陽電池の開発につぎ込むわけだ。この際、同会計の歳出を全面的に見直し、もっと将来を見据えた戦略的な運営に変えていくべきだ。この1兆円の投資はまったく惜しくない。なぜなら、これほどリターンの高い投資はないからだ。しかも、次世代のエネルギー覇権がかかっている。よって、これは国策として直ちにやるべきである。
先日の日経新聞によると、本年度で中国などの海外メーカーが、国内の太陽電池市場の3割を獲得してしまうそうだ。おそらく、メガソーラー建設ラッシュが始まると、彼我の比率が一気に逆転するだろう。国内シェアの7、8割を中韓企業などが占めるようになる。メガソーラーを整備すればするほど、われわれ消費者の金は彼らの懐に向かうわけだ。得をするのは発電ベンチャーと海外企業だけ。本当は、現在のシリコン系太陽電池でさえ、中韓メーカーがそう簡単に作れるような代物ではなかったのだが、安易な技術指導や国際協力という名の下の善意によって、製造技術がどんどん流出してしまった。その結果、自分たちの首を絞めている。われわれはこの種の過ちを今まで何度繰り返してきたことか。次世代太陽電池では、その過ちを二度と繰り返してはならない。これはそうそう簡単に開発できない。この技術は国家機密として、絶対に譲り渡すべきではない。
日本が一番乗りで「光の可採化」に漕ぎ着けるべきだ。その時、われわれの眼前に信じられないような未来が開けるだろう。そのインパクトについては、次回に持ち越したい。
2012年04月16日「アゴラ」掲載




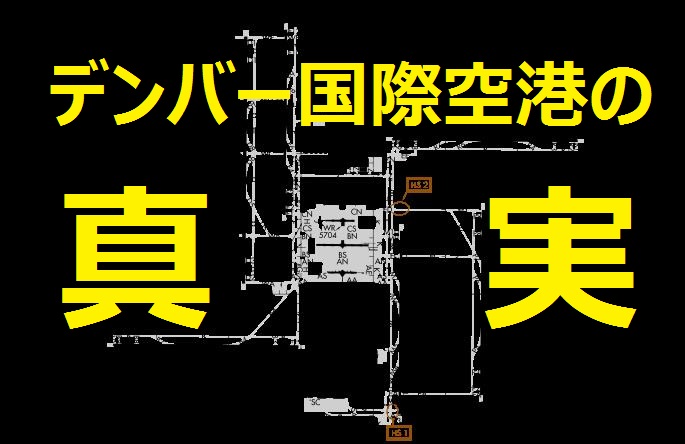







スポンサーリンク