水素エネルギー論者の中には、水素こそ持続可能なエネルギーシステムの核となりうると考える人が少なくない。水素は地球圏にほとんど存在しないが、原料が水であるため、無尽蔵に存在するに等しい。しかも、直接燃やしても、燃料電池に投入しても、どちらにしても酸素と化合するために、排出されるのは水だけであり、環境を汚染しない。
この点に着目した海外の学者が唱え、世界中の環境主義者に広まったのが、再生可能renewableという意味での「R水素」という概念である。水素エネルギー社会を待望する人の中には、一定の割合でこのR水素を信奉する自然エネルギー論者が存在している。
彼らの主張は次のようなものだ。太陽光や風力は豊富にあるが、天候次第という欠点がある。そこで、それらの供給力が需要をオーバーしている時などに、その余剰電力を使って水を電解する。そうして製造した水素は、逆に供給力が需要に届かない時などに、燃料電池などのエネルギー源とする。こうすれば、不安定な太陽光・風力発電の欠点が補える。しかも、この種の水素は、単に自然エネルギーの保存だけでなく、自動車のエネルギーや化学原料としても使えるので、石油の代わりにもなる。よって、自然エネルギーとそれに拠る「再生可能水素」の利用を拡大していけば、最終的には脱化石エネルギー、つまり持続可能な「カーボンフリー」社会を築き上げることができる…こんなところである。
このような理念は、そもそも「電気は保存できない」又は「し辛い」という“常識”から来たものだ。われわれ需要家にとって、電気というのは必要な時に必要な量がなければ意味がない。ところが、太陽光や風力は気まぐれに発電するため、そのニーズに十分に応えることができない。よって、自然エネルギーで作った電力をいったん「水素」に転換しておけば、エネルギーの保存と電力の需給調節、他の目的での使用等が可能になるというわけだ。
わざわざR水素で太陽光や風力を保存する必要はない
つまり、これは「蓄電池の代替案」なのである。ところが、この考えにはある重大な思い違いというか、はっきり言えば「無知」が存在している。そして、不可解なことに、私の知る限り、今までそれをはっきりと指摘した専門家は誰もいない。
それは、こういうことである。たしかに大電力を保存することは、今日でも至難の業だ。だから、負荷平準化のために、数割のロスを覚悟してまで、揚水発電などが利用されている。だが、このような土木工事を伴う「巨大蓄電池」は何千億円もの整備費を要し、環境規制もあるため、そうホイホイと造れるものではない。ところが、同じ100万kWの発電所から生み出される電力であっても、火力・原発由来のものならば、揚水発電によって蓄エネする他ないが、太陽光と風力であれば、必ずしもその必要はないのだ。なぜなら、メガソーラーもウインドファームも「モジュールの集合体」だからである。
ここが巨大なタービンとダイナモから巨大電力を生む火力・原発との違いである。たとえ、その発電所が500万kWや1千万kWの巨大出力を誇ろうとも、元はといえば、1基の風車、1枚の太陽光パネルから構成されている。風車の出力はせいぜい3~5千kWだし、太陽光パネルもそれと同程度の出力ごとに分割することができる。そして、そういった「小電力」ならば、比較的容易に蓄電が可能なのだ。
皮肉なことだが、「エネルギー密度が低い」という太陽光や風力の欠点が、電力貯蔵の上では逆にメリットと化すのである。しかも、発電所に併設する電力貯蔵施設は、自動車ほど空間の制約を受けない。つまり、エネルギー密度が低く、図体が少々デカくても構わないのである。よって、自動車用としても有望な溶融塩電解液電池や金属空気電池などは言うに及ばず、NAS電池、レドックスフロー電池、電気二重層キャパシタなども大いに活用できるのだ。このように、今では小電力の保存に適した実用的な蓄電池・キャパシタなどが次々と登場し、現に一部の発電所で貯蔵用として導入され始めている。
つまり、「電気は保存し辛い」という“常識”は、少なくとも小電力に対しては、とっくの昔に当てはまらなくなっているのである。
蓄電池の技術は今も日進月歩だ。このまま蓄電池の性能とコストが改善していけばどうなるか、この点に少しは想像力を働かせてもよいのではないだろうか。当然、太陽光や風力によって発電した電力は、わざわざ水素に転換するという無駄なことをせずとも、そのまま蓄えておけばよい。しかも、貯電能力次第では、短期的な出力変動のみならず、「昼夜→数日間→一週間超」といったレベルの負荷平準化にも対応できるようになる。これはダム式水力に極めて近い性質の電源を意味する。そうなれば、太陽光や風力発電は、もはやバックアップのいらない「自立した一人前の電源」だ。
しかも、この種の「高性能蓄電池とセットの太陽光・風力発電」の普及は、「クリーンで持続可能な国産エネルギー」を増加させるだけでなく、電力システム全体を筋肉質に改善する効果をも持ち合わせている。日本の電力需要は約1兆kWhであるため、本来なら1億4千万kW強の発電設備が年間8割稼動していれば賄える。ところが、大電力の一部しか保存できないため、負荷変動に対応しきれず、1億8千万kWの夏ピークに合わせた設備を整えることを余儀なくされている。それによって日本は約4割もの過剰設備を強いられているのだ。しかし、上のような新式の太陽光・風力が普及していけば、需要ピークに合わせたこれまでの電源整備から、年間消費量に合わせた整備へとシフトしていく道が開けよう。例えるならば、これは漁業に冷凍庫が登場したような革命である。
むろん、今の蓄電池の性能とコストからすると、ピーク対応の予備電源を設置するのとさして経済性に違いはないかもしれない。しかし、それが改善していくにつれ、蓄電池併設の有効性は高まる一方となるだろう。「お天気任せの太陽光や風力」という悪評が過去のものとなるばかりか、それが普及するにつれ、電源の設備過剰という構造的な問題も少しずつ解消されていくのだ。そうすると、今の段階で、ドイツ式のFITなどを使って「蓄電池なき太陽光や風力」を“爆発的に普及”させることが、果たして正しいのかという疑問が沸いてくる。しかも、わざわざ電解水素を作って需給調節しようというのだ。このような行為が、何か二重、三重に間違っているように思えるのは私だけだろうか。
結局、R水素の出番はあまりない
ましてや、R水素で燃料電池車や水素内燃車を走らせるとなると、これはもう完全にジョークの域である。すでに二次エネルギーである電力で水素を作ると、それは三次エネルギーである。その水素を燃料電池に投入し、さらに電気を作るとなると、消費端では「四次エネルギー」と化す。仮に三次エネの水素を内燃車に投入し、直接燃焼させたとしても、内燃機関自体のエネルギー利用効率が悪いので、総合効率でいえば、四次エネで走る燃料電池車とほとんど大差ないと思われる。
これが「石油の代わりになる」と考えている人は、おそらく持続可能性の獲得にプライオリティを置くあまり、エネルギー収支比を無制限に犠牲にすることも厭わないタイプであろう。だが、太陽光や風力による電解水素の生産・流通・消費システムを社会に固定化させてしまった場合、エネルギーはとんでもなく高価になり、われわれは生活水準の大幅な切り下げを余儀なくされるに違いない。だいたい、エネルギー効率が内燃自動車よりも著しく劣っていれば、それはもはや文明の後戻りである。よって、私はrenewableの代わりにridiculous意味で「R水素」(イカレ水素)と呼ぶことを提唱したい。
このように、R水素は、自然エネルギーの保存方法としても、自動車用燃料としても、著しく合理性を欠くのである。太陽光や風力による電力は、優れた蓄電池でそのまま保存し、供給の安定化を図りつつ、EVなどのエネルギー源として利用するのが科学的にも正しいと思う。とすると、最後に残る関門は「マテリアル利用としてどうか」である。
これも、あまり需要はありそうにない。というのも、近年、バイオ燃料とバイオガスの生産技術が急速に進歩しているからである。今日、石化製品は、石油質のバイオ燃料・バイオメタン・植物原料などの持続可能性素材から、誘導生産することができる。もちろん、化学・工業原料としての水素のニーズはあるが、依然として流通コストに難がある以上、今よりも極端に大規模化するとは考えられない。とすると、結局、R水素なるものは、石油の代わりとして新たに社会や文明の「コア」を担うどころか、素材部門の一角を占める程度がせいぜいだと思われる。このように、現実には、将来的にもR水素の出番はほとんどないと考えられるので、このような概念にあまり固執すべきではない。
“水素エネルギー社会”の神話は崩壊した
一部には、定置式の燃料電池が普及した社会を強引に“水素エネルギー社会”と見なす向きもあるようだ。だが、これは苦しい見方である。実際に行われているのは、あくまでメタンなどのガスの生産・貯蔵・輸送である。これならば水素と異なり、簡単・安全で、特別な技術や追加投資もいらない。消費端でそのガスを直接燃やそうが、あるいはオンサイトで水素を抽出して発電しようが、それはあくまで消費者の選択でしかない。しかも、今後、自動車の本命はあくまでEVであり、燃料電池車や水素燃料の流通は、少なくとも全国レベルではありえない。そうすると、このような社会は「ガスと電力」によって支えられているのであって、決して“水素エネルギー社会”ではない。
自然エネルギーの保存方法として不適切で、自動車のエネルギー源としても欠格である以上、今後とも水素がエネルギーの主役になったり、水素を中心とした社会インフラが出来上がったりする可能性はない。あくまで部分的・地域的な利用に留まるだろう。いかに持続可能であっても、必然的に高価にならざるをえないエネルギーは、われわれの暮らしをかえって貧しくする。人が合理的な選択をする以上、もっとシンプルで効果的な別の方法が好まれるに違いない。
以上、いかに学者・官僚・著名人が大真面目に水素エネルギー社会を提唱していようとも、そのようなものが実現する可能性はほとんどない。彼らはNAS電池の登場あたりで、自分たちの主張が根拠を失ったことに気づくべきであった。これは「理念倒れ」、つまり「コンセプトとしての敗北」である。おそらく、ポスト石油文明の過渡期に現れては消えていく候補の一つなのだろう。
このシリーズで何度も訴えているように、自覚的に脱石油を進めていくと、必然的に天然ガスが一次エネルギーの主役になるというのが、私の説である。私はこれを指して「メタン文明」と呼んでいる。それは石油文明よりは安泰で、はるかに居心地のよいものだ。だが、技術の進歩は留まるところはなく、私の予測では、メタン文明へのシフトが完了してから早くも数十年以内には、今度は自然エネルギーが主役の座を射止めるだろう。しょせん持続不可能なメタン文明は、現れてはすぐに過ぎ去っていく通過点のようなものである。
おそらく、2050年頃には、日本は「エネルギーの永久自給国」というゴールにかなり近づいているものと思われる。家庭や企業が使うエネルギーの大部分は、自然エネルギー由来の電力・バイオ燃料・バイオガスなどで占められるだろう。水素はエネルギーや素材の一角を担っているかもしれないが、それだけの話であり、“水素エネルギー社会”と呼ぶまでには至らない。やはり近未来のエネルギーの中心を担うのは、太陽光・風力・地熱などの自然エネルギーであり、それらが生み出す力強い電力である。
さて、蛇足である。
この“R水素騒動”を眺めて改めて感じるのは、エネルギー問題とはまた違った次元の、社会心理学的な問題である。周知の通り、海外発の最新のコンセプトに何の疑問も持たずに飛びついて、国内向け代理人の地位にいち早く納まり、「我こそは世界の流行の最先端にいる者だ」というオーラを同胞に向けて発散させることが、昔からの日本の進歩的知識人の習性である。また、大半の日本人も、三つ葉葵を突き出されたかのように、「ははーっ」と海外権威の威光に盲目的にひれ伏してしまう。そのことを思えば、あながち個人にばかり責任を着せられない。
最近の言葉では、こういうのを“辺境者意識”というらしい。要するに田舎者のメンタリティである。残念ながら、自然エネルギー論者にもそういう人たちが多く、二言目には「ドイツに学べ」「日本は世界から取り残されている」と叫んでいる。
だが、私はあくまで逆を訴える。「日本はバスに乗るな」と。日本はあくまで独自の自然エネルギー戦略を考え、それを粛々と実行していけばよいのである(*むろん、かく言う私もちゃんと考えてあるので、それは近々発表していきたい)。
2012年04月02日「アゴラ」掲載
(再掲時付記:電気は普通に蓄電池で貯めましょう。)



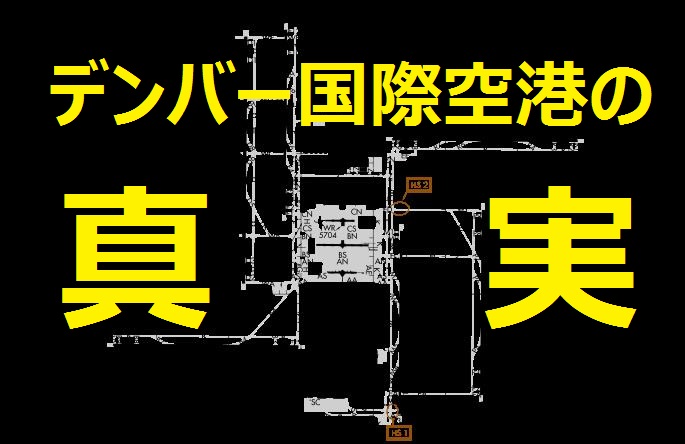








スポンサーリンク