中央銀行には通貨を発行する権限がある。それがいかに凄いか。たとえば、私たちの1万円札の「万」の漢字を「兆」に変えて日銀が印刷すると、それは本物の1兆円札となる。紙切れ一枚が1兆円・・・。「そんな馬鹿な!?」と思われるかもしれないが、それが日銀券である以上は「本物」である。裏づけとして政府の信用さえあればいい。むろん、これはあくまで例えだが、要は通貨発行権とはそういうものだ。
基本的に、ある通貨の価値は、社会的要素を除けば、実体経済の規模と流通量との比率で決まる。だから「供給」(マネーサプライ)の権限を握れば、貨幣価値を決める権限を握ったも同じだ。そして「金利決定権」を握れば、原理的には(金融自由化以降は預金金利との間に直接の連動性は無くなっているが、それでも実態として)すべての銀行とそこから借りている企業と個人の経済活動すらも左右できるようになる。
このように通貨の発行・金利決定・供給量等を担う「中央銀行」を作ることにより、その国の経済全体をコントロールすることが可能になった。このような概念を生んだ近代経済学又それを生み出したユダヤ人経済学者の頭脳には、改めて驚嘆せざるをえない。
■祖国を持たない国際銀行家たち
しかし、逆にいえば、この権限を悪用すれば、一国の経済を「刈り取る」ことすらも可能になる。だから、この通貨発行権を求めて血みどろの抗争が行われてきた。
もっとも、最初にこの原理に気づいた者のほうが、競争において有利である。とくにヨーロッパでは、金融業は特定のマイノリティに偏っていた。それがユダヤ人だ。
神聖ローマ帝国だけでも数十種類の通貨が流通していたと言われる。こういったヨーロッパ通貨の交換業務を担っていたのがユダヤ人両替商だった。彼らは中世以来、両替商ビジネスや各国の経済政策に関わるうちに、今日の経済学のベースとなる発見をほとんど成し遂げた。そして最先端の金融の知識と技術を内々で積み重ねてきたのである。

ザムゾン・ヴェルトハイマー(Samson Wertheimer, 1658年~1742年)神聖ローマ帝国屈指の宮廷ユダヤ人・銀行家で、ロスチャイルドの先輩格に当たる。
さて、彼らユダヤ商人たちは、フランス革命を経て正式に市民権を得て、もはや君主の気まぐれで私有財産を没収される心配もなくなった。依然として帝政ロシアでは圧政下に敷かれていたものの、ウィーン体制が成立した1815年には、ほぼ欧州全土で市民権を得ることに成功し、もはや自宅の床下に穴を掘って財産を隠す必要もなくなった。
そして、彼らは堂々と「表の世界」に出て、もはや「宮廷ユダヤ人」ではなく「銀行家」として活躍するようになったのである。しかも“祖国”を持たない“国際銀行家”だ。
以後、彼らがいかに欧米での戦争・恐慌を使嗾し、いかに金を儲けてきたか、本題ではないためここで詳しく語るスペースはない。皮肉なことに、キリスト教が金利収入を悪徳と見なし、ユダヤ人に「汚れ仕事」をやらせたことが、彼らにマネーパワーを与えたのだ。
英米、独仏、ロシア・・いずれも酷い目に合っているが、一つだけ例示すると、1929年のNY株暴落は彼らの陰謀の中でも傑作の一つであった。彼らは株を暴落させ、後に底値で買い漁ることによって、米経済を丸ごと刈り取ってしまったのである。
そんな恐るべき連中が1970年代に目をつけた国があった。日本である。
■日本の富を「刈り取る」ために80年代に実施された仕込み
より広い見方をすれば、日本から富を収奪する計略は、1972年にロックフェラー邸で開かれた米日欧三極委員会(トライラテラル)創設会議からスタートしたと見ることもできる。なぜなら、この時点で意図的か否かはともかく、いったん欧米諸国の仲間として日本を引き入れたことが、のちの合法的な横領の成功へと繋がったからである。
遅くとも、この三極委員会メンバーで埋め尽くされたカーター政権の末期、つまり1980年代に入る頃には、国際銀行家たちによる「日本刈り取りプラン」はすでに完成していたようだ。発動は次の日米新政権である。81年、ロナルド・レーガンが大統領に、そして82年、日本側のカウンターパートとして中曽根康弘が総理大臣に就任する。中曽根氏は若手政治家時代からロックフェラーやキッシンジャーと旧知の間柄だった。

また、レーガン政権にはあるキーマンがいた。それがメリル・リンチ元CEOのドナルド・リーガンである。レーガンが全幅の信頼を置いたウォール街の代弁者であり、財務長官に就任するや法人税引き下げなどの“レーガノミックス”を推進した。
レーガン政権は発足早々、日本に対して「安保タダ乗り」や「貿易不均衡」などを盛んに言い立て、貿易制裁をチラつかせては、市場開放を強く要求した。こういった外圧で設置されたのが83年の「日米円ドル委員会」である。ところが、実態は両国の「協議」とはほど遠く、日本側が直ちに飲むべき要求項目がすでに出来上がっていたという。
端的にいえば、それは日本の金融市場の開放を強く迫るものだった。協議は異例のスピードで決着し、様々な規制の緩和、外資に対する参入障壁の撤廃、円の国際化、先物・オフショア市場の創設などが約束された。これにより外資上陸の準備が整えられた。
今にして思えば用意周到な罠だったわけだが、当時は金融や経済の「国際化」という美名に置き換えられた。そして、中曽根総理もまた経済政策の目玉として「規制緩和」と「民営化」を掲げ始めた。
85年9月、先進五カ国蔵相・中央銀行総裁会議がニューヨークのプラザホテルで開催された。これにより円は200%もの円高へと向かう。日本のドル国富が目減りし、日本企業の輸出力が弱体化する一方、ロスチャイルドからカリブ海のタックスヘイブンの資金運用を任されたジョージ・ソロスは、猛烈な円買いドル売りで空前の儲けを手にした。以後、ソロスは「ロスチャイルドの鉄砲玉」として国家主導の金融システムを攻撃し続ける。一つの目的は、各国をグローバルな経済連携へと向かわせるためだ。
86年には米証券会社が東京証券取引所の会員になり、以来、外資系証券が続々と日本の金融市場に上陸を開始した。87年、大蔵省がNTTの株式を市場に売りに出した。日本電信電話公社の民営化は、国鉄のそれと並び、中曽根内閣の民営化政策の目玉である。いわば「お上推奨」の株取引だった。たちまち「NTT株で何百万円儲かった」などの話が巷間に溢れ、普通のサラリーマンや主婦の間にも投機熱が高まった。
88年、国際金融システムの安定化を名目に、国際取引をする銀行の自己資本比率を8%以上とする「バーゼル合意」(いわゆるBIS規制)が決められる。奇妙なことに、邦銀には自己資本に一定の「株の含み益」を組み込む会計が認められ、これが自己資本率の低い邦銀をして、ますます株上昇への依存に走らせた。しかも、やや先走るが、バブル崩壊後は、今度は「93年から規制適用」のルールが不良債権問題悪化や「貸し渋り・貸し剥がし」の要因となり、日本経済をさらにどん底へと追い込んでいった。
■バブル経済はこうして生まれ、急激に崩壊させられた
ここで日銀の金利政策を振り返ってみよう。
1980年3月、公定歩合は9%だった。つまり、当時は銀行に100万円を預けると、1年後には109万円になるという、羨ましい時代だったのだ。
ただ、この金利は毎年のように引き下げられ、87年2月には、80年代を通して底となる2・5%をつけた。今日のゼロ金利時代からすると、それでも預金に殺到したくなるほどの“高”金利だが、当時としてはこれが「戦後最低金利」だった。
とくに80年代後半の利下げには、プラザ合意による急激な円高も関係していた。当時「円高不況・国内空洞化」が懸念され、大蔵省も日銀に利下げを要請したのだ。
一方で、通貨供給量は80年代後半から年間10%(だいたい数十兆円)レベルで増やされた。当時は国債の発行高も少なく、金融も今ほどグローバル化していなかった。
その結果、膨大な低利の資金の大半が日本国内の債権と土地に向かった。
当時、株と土地を買うと、誰でも儲かった。銀行は普通のサラリーマンや公務員、主婦にまで融資した。「NTTの株で数千万円儲かった」とか、「土地の転売だけで数億円儲かった」などの話が、誰の周辺にも転がるようになった。銀座のクラブでは毎晩札束が飛び交い、証券会社の20代社員が数百万円ものボーナスを貰った。高級ブランドの購入や海外旅行が当たり前になり、日本全体が熱に浮かされたようにバブル経済に踊った。

ジュリアナ東京の様子
一方、まさにこの頃、金融自由化の下、外資が続々と日本に上陸していた。
この「戦後最低金利」は89年の半ばまで続けられた。だから、80年代の初期から見ていくと、「80年代を通してずっと金融緩和・景気刺激策が行われた」とも言える。
ところがである。やがて、あまりの土地の高騰などが批判されるようになる。それが本当の理由か否かは不明だが、まさにバブル経済が膨れ上がったところで、日銀は、今度は一転して金融引き締め政策へと大転換した。しかも、89年半ばから、わずか1年3ヶ月という短期間で、2・5%から6%へという、異常な引き上げを実施した。
これだけ短期間での急激な利上げは、今にして思えば暴挙としか言いようのない政策だった。住宅ローンなどで多額の借金をしている人は、金利が上昇すると、どれほど返済に苦労するか、よくご存知だろう。当時、急激な金利の上昇を受け、法人・個人は新規の借り入れを手控えた。また、返済額の急上昇により、多くの投資家が「手仕舞い」を強いられた。その「損切り」の売りが、また売り呼ぶという負のスパイラルが始まった。
しかも、日銀は、90年代に入るや、やはりそれまでとは一転して、今度はマネーサプライのほうも急減させた。元栓そのものが絞られたので、銀行も融資を減らさざるをえなくなった。つまり、金利と通貨供給量の両面で、日本経済は急ブレーキを踏んだのだ。
さらに、その少し前に、ソロモンブラザーズ、モルンガン・スタンレー、ゴールドマン・サックスなどが内外で大量に売り捌いていた数十本ものプットワラント商品が、日経株価に対するレバの効いた空前の売り圧力として作用し始めた。東証株式市場は雪崩を打ったように崩壊し始め、市場関係者はパニックに陥った。著名な株価評論家や相場師までが大損し、誰もが「市場で何が起こっているのか分からない」と首を傾げた。

9・11の際に火災が発生し謎の自動崩壊を遂げたソロモンブラザーズビル
日銀と外資だけでなく、大蔵省までが軌を一にして急ブレーキを踏んだ。それが1990年3月に実施された「不動産総量規制」という金融機関への行政指導である。簡単にいえば「不動産向けの融資を減らせ」という内容だが、当時、大蔵省銀行局長の通達といえば命令と同じである。不動産価格の高騰を抑えるのが目的だったが、銀行から融資を受けて不動産に投資していた事業家にしてみれば、いきなり元栓を締められたのと同じだった。
このように、主として「日銀の金融政策」「外資による空売りの仕掛け」「大蔵省の銀行指導」という三つの要因によって、バブル経済は突然崩壊させられたのである。
結果として、日本に金融市場の開放をねじ込んだ当事者たち――ウォール街とその手先――に史上空前ともいえる所得移転がもたらされたのであった。
2016年11月8日「トカナ」掲載
(*題名・見出し等は少し変更してあります)
(付記:私は「国際銀行家たちの陰謀」と題していたのですが、アップされたものを見ると「ユダヤの陰謀」に変わっていました・笑)









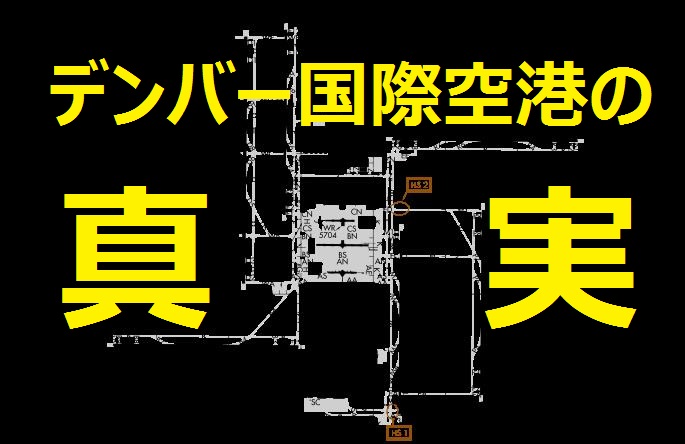


スポンサーリンク