ユダヤ人の支配層は4千年の歴史でモノを見る。この辺の感覚は中国人のそれと似ているかもしれないが、違いは彼らの場合、辺境・被支配の立場に当たることだ。
古代オリエントでは、ナイル川とチグリス・ユーフラテス川の巨大平野を中心として大文明が栄えた。その狭間にあって、万年属国をやっていたのがイスラエルなのだ。
そのユダヤ人の目線で見てみよう。どうやら彼らには、現代の地域情勢がそのまま古代のそれと被って見えるらしい。中東の場合、古代とほとんど風景が違わないことも関係しているのかもしれない。それが、時間が静止しているというか、古代と現代がダブって見えるという、特有の時間感覚を生む一因なのかもしれない。
つまり、ユダヤ人の目には、自分たちを奴隷や属国としてこき使ってきた古代エジプト・古代シリア・古代バビロニアなどは、そのまま現代のエジプト・シリア・イラクと重なって見えるらしいのだ。これは旧約聖書などを通して当時の屈辱体験を常に追体験してきたこととも無関係ではあるまい。日本人からすると、異常な執念深さである。
だから、ユダヤ人の心理をよく考える必要がある。現代のイスラエルは、それらの末裔の国々を、次々と撃破してきたのだ。古代と現代を重ねて見る彼らにしてみれば、それは古代のライバル帝国を先祖に代わって撃破してきた行為に他ならない。
アメリカを動かして周辺諸国を次々と打倒
むろん、この辺りの経緯は、イスラエル本国というより、むしろグローバル・ユダヤが主導してきたといえる。たとえば、9.11前から、「見えざる政府」の手下であるチェイニーやラムズフェルドなどを中枢メンバーとするPNAC(ピーナック:アメリカ新世紀プロジェクト:Project for the New American Century)は、中東での戦争・占領計画を立てていた。そこへ「偶然」にも9.11テロが起こり、ブッシュ政権で国防長官となっていたラムズフェルドの統帥下、アメリカは対アフガン・イラク戦争へと突っ走る。
この辺りには、イスラエルの安全保障だけでなく、石油利権も絡んでいた。いわば彼らにとって「一石二鳥」の戦略だったわけだ。
だが、イランが総力を挙げて米軍のイラク占領統治をサボタージュしたせいで、米国内の世論の風向きが変化する。イランにしてみれば、次は自分が攻撃される番なので、必死の妨害である。その他にも複数の理由があって、「見えざる政府」はネオコンをいったん後退させたわけが、もともとの計画では、イラクを占領した後、そこを拠点にして、イラン・シリア・レバノン・リビア・スーダンなどを侵略する予定だった。
見事なまでにイスラエルの周辺諸国ばかりである。むろん、攻撃対象国には“悪の枢軸”の一員たる北朝鮮も含まれていたが、その主な理由はイランと核・弾道ミサイル開発で事実上の同盟関係にあったからであり、日本の安全保障のためではない。
おそらく、「見えざる政府」が戦略の軌道修正を行ったのが2005年の後半。この年にプーチン・ロシアと胡錦濤の中国が対米同盟を結び、「新冷戦」をスタートさせたこととも無関係ではあるまい。ただし、戦略の転換といっても、「戦争」というダイレクトな方法から「謀略」という陰湿な方法へと乗り換えただけの話である。それが表に出てきたのが、2010年以降の「アラブの春」なる社会現象だった。戦争とは異なり、民衆による革命=民主化運動というふうに宣伝すれば、世論も反対しないというわけだ。
こうして、今ではイスラエルの周辺国ばかりが内乱・内戦で没落しているのである。
なぜ「打倒ペルシア」なのか?Why does the Jew want to defeat Persia?
いずれにしても、ユダヤはこうやってアメリカまでもを自在に動かし、先祖に代わって仇を討ってきた。
彼らが今、どれほど精神的に高揚していることだろうか。しかも、そこにはおそらく「宗教的情熱」も含まれている。というのも、旧約聖書によると、終わりの時には、イスラエルがそれらの国々を従え、盟主になることが預言されているのだ。
聖書時代のユダヤ人にしてみれば、周辺の帝国はあまりに強大だったので、いかに神の言葉とはいえ、まったく現実味のないホラ話に等しかったに違いない。
ところが、今まさに、神がユダヤ民族に約束したこと、つまり「契約」が実現しようとしているのである。彼らが内心でどれほど高揚していることか。だからユダヤの支配層は、同時に「終わりの時」が近づきつつあることもひしひしと実感しているはずだ。
しかしながら、まだ最後の障害が残っている。実はそれこそがペルシア(イラン)なのだ。それゆえ、「あとペルシアさえ打倒すれば・・・」というユダヤ人の奇妙な宗教的情熱を理解しない限り、あの異常ともいえる「打倒イラン」の執念も理解することはできない。そこにはコンプレックスむき出しの悪意さえ込められている。
「大イスラエル構想」の原型は古代ペルシア帝国 The model of “the great Israel” is ancient Persia
もし典型的なユダヤ人のペルシア観を知りたければ、あの『300(スリー・ハンドレッド)』というイラン人大激怒のハリウッド映画を見ることをお勧めする。ちなみに、配給は(ユダヤ人の)ワーナー兄弟の会社である。
一見して、観客がペルシアに強い偏見を持つように仕向けた政治的な映画だと分かる。スクリーンではペルシアが極めて道徳的に堕落した異様な帝国として描かれている。登場するペルシアの支配層は、人間というより、ほとんど妖怪である。

出典:映画『300(スリー・ハンドレッド)』
しかも、偏見に輪をかけて悪質なのが政治的なメッセージだ。なんでわざわざペルシア戦争を描くのか。それは「イランは西洋文明の敵だ」とか「西洋とは相容れない異質な存在だ」などと、欧米の観客に刷り込むためである。それで西洋文明の生みの親であるギリシアを引っ張り出してきて、古代における「文明の衝突」を描いた。こうやって、欧米と中東を分断し、常に相争わせる・・・まさにユダヤの深慮遠謀である。
対して、事実はどうだったのだろうか。実際には、アケメネス朝ペルシアといえば古代世界屈指の大帝国である。最盛期にはバビロニアとエジプトまでもを支配し、古代オリエントを統一した当時の世界帝国だ。壮麗なペルセポリス宮殿跡やゾロアスター教の中身を吟味すれば、物質的にも精神的にも当代随一の文明を誇っていた事実がよく分かる。
しかも、このペルシアのキュロス大王(キュロス2世:イランでは建国の祖とも考えられている)のおかげで、ユダヤ人は新バビロニアの奴隷の地位から解放されたのだ。
ウィキペディア「キュロス2世」は次のように記す(*傍線は筆者)。
東方各地を転戦して征服し、紀元前539年にオピスの戦いでナボニドゥス率いる新バビロニア王国を倒した。10月29日にバビロンに入城して[3]「諸王の王」と号し、バビロン捕囚にあったユダヤ人をはじめ、バビロニアにより強制移住させられた諸民族を解放した。キュロスは、被征服諸民族に対して寛大であったので、後世に理想的な帝王として仰がれ、ユダヤ人を解放して帰国させたことから旧約聖書ではメシア(救世主)と呼ばれている(イザヤ書45章1節)[4]。またこのとき、キュロスは新バビロニアのネブカドネザル2世によって略奪されていたエルサレム神殿の什器を返還し、エルサレムに神殿の再建を命じた。この再建は難航し、紀元前520年ごろに第二神殿が完成した時にはキュロスはすでにこの世を去っていたものの、この恩とキュロス以降も継続された宗教寛容政策により、ユダヤ人はアケメネス朝の統治下においては一度も反乱を起こさなかった。

キュロス2世のバビロン侵攻直前の古代近東 出典:同ウィキペディア

キュロス2世戦没時のアケメネス朝領土 出典:同ウィキペディア
奇妙なことだが、今になってみれば、そのことがユダヤ人にとって屈辱らしいのである。だから劣等感を炸裂させて、古代オリエントにおけるもっとも偉大な帝国を、あんなふうに意地悪く、退廃的なサタニズム国家として描いたのだ。自分たちの恩人をこんな風に醜悪に描くのだから、いかにねじくれたメンタリティであるかが分かる。
逆にいえば、ユダヤ人にとって、それだけ羨望の対象なのである。彼ら自身は認めないが、古代ペルシア帝国こそ彼らの「大イスラエル」のモデルであることは明らかだ。
エゼキエル預言の時の近づきを予感するユダヤと福音派
つまり、ペルシアとは、彼らにとって永久にコンプレックスの種となりかねない存在なのだ。だからこそ、万年属国民だったユダヤ人としては、ペルシアを打倒して自らが成り代わらねばならない。彼ら自身の劣等感を払拭するためにも。
しかし、それは同時に「終わりの時」が近づいている証左でもある。その「終わりの時」の最終イベントこそが、実は「ロシア・イラン連合軍がイスラエルに攻めて来る」(*厳密にはそういう解釈)というものなのだ。下はその参考記事である。

もう、ユダヤ人も、欧米人も、このことを意識している。
その時、「神」は火でロシア連合軍を滅ぼす。そして、彼らの神が現れる・・・らしい。ヒンドゥ・シントーニストの私からすると、付き合いきれない。
しかも、これを同じ様に熱狂的に支持しているのが、アメリカの宗教右翼・福音派である。ただし、彼らにとって、現れるメシアはイエス・キリストなのだ。
日本人からすると、何もかも正気の沙汰ではないが、イスラエルを偏愛するトランプが大統領になったことで、「イスラエルVSイラン戦争」が一挙に現実味を帯びてきた。

欧米の政治家も軍人も口にこそ出して言わないが、この預言を意識しているのだ。







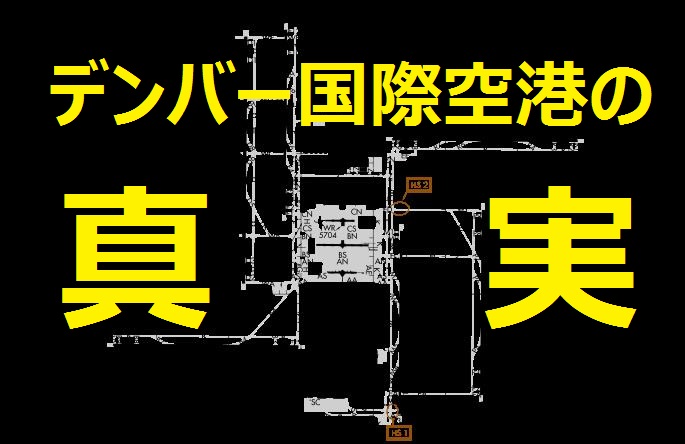




スポンサーリンク